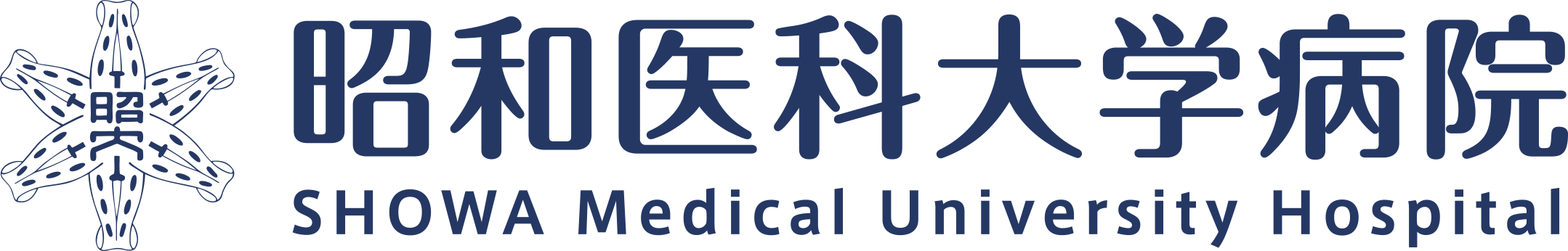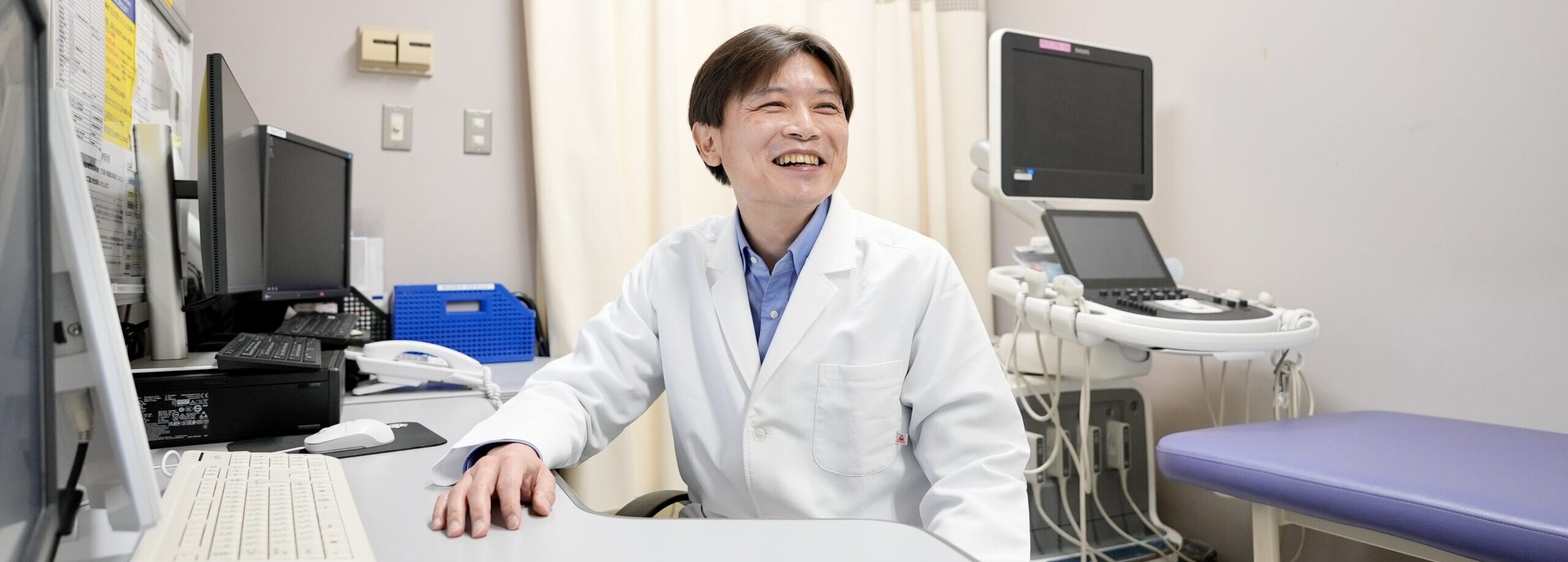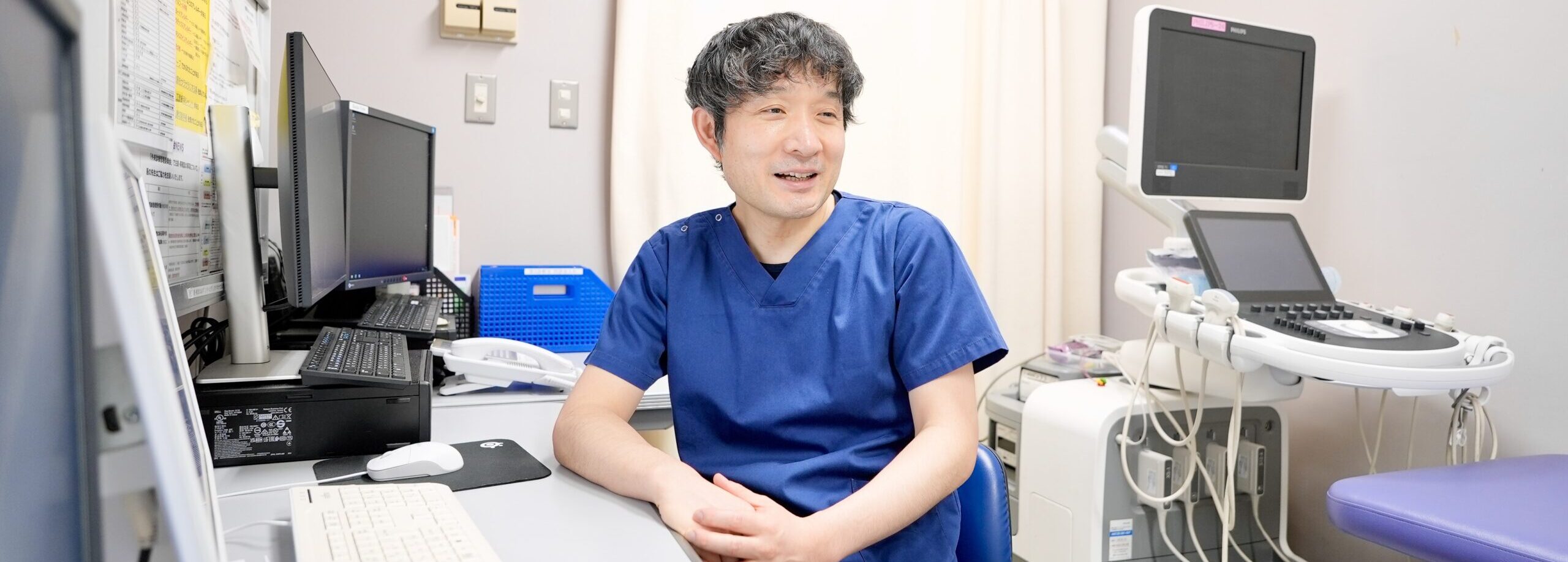小児のエプスタイン病について
―お子さまの「右心房と右心室の仕切りに異常がある病気」をやさしく解説します―
1. エプスタイン病とは
エプスタイン病(エプスタイン奇形、Ebstein’s anomaly)は、赤ちゃんや子どもに見られる「先天性心疾患(生まれつきの心臓の病気)」の一つです。
心臓の右側にある「三尖弁(さんせんべん)」という弁の位置や形に異常があり、右心房(うしんぼう)と右心室(うしんしつ)の仕切り(弁)が本来より下がった位置についてしまっているのが特徴です。
【正常な心臓の場合】
- 三尖弁は右心房と右心室の間にしっかりとあり、血液の流れをコントロールします。
- 右心房で集められた血液は三尖弁を通って右心室へ流れ、その後肺へ送られます。
【エプスタイン病の場合】
- 三尖弁の弁の位置が右心室側へずれて下がっている
- 弁の形が薄い・大きい・奇形になっていることも
- 結果として、右心房が大きく、右心室が小さく(発達不足)なりがち
- 血液が心房と心室の間で逆流しやすい
2. なぜ起こるの?
エプスタイン病は、お母さんのお腹の中で赤ちゃんの心臓が成長する過程で三尖弁の形成がうまくいかなかったために起こります。明らかな原因はほとんどの場合分かっていません。
まれに他の心臓の病気や、妊娠中の薬剤使用(特にリチウム製剤)との関連が指摘されることもありますが、多くは偶然に起こるものです。ご両親の責任ではありませんので、自分を責める必要はありません。
3. エプスタイン病があるとどうなるの?
エプスタイン病の程度(重症度)はお子さんによって大きく異なります。
□ 血液の逆流(逆流症)
- 三尖弁の閉じ方が悪く、右心室から右心房へ血液が逆流しやすくなります。
- そのため、右心房が拡大し、右心室が十分に大きくならないことが多いです。
□ 心房中隔欠損(ASD)など他の病気の合併
- 多くの場合、「心房中隔欠損症」など心臓の他の部分にも穴が開いており、酸素の多い血液と少ない血液が混ざることがあります。
- このため、全身に送る血液の酸素が足りなくなり、「チアノーゼ(皮膚や唇が青紫色になる)」が起こりやすくなります。
□ 心臓の働きの低下
- 右心室が小さいと、肺への血流が少なくなり、酸素が足りなくなる
- 心臓に負担がかかり「心不全」になったり、全身の発育や成長が遅れることがあります
□ 不整脈
- エプスタイン病の子どもは「不整脈(心臓のリズムの異常)」を起こしやすい特徴があります。
- まれに、突然の動悸や息切れ、失神などが見られることも
4. どんな症状が現れるの?
症状の強さは病気の重さや合併症の有無によって違います。
□ 新生児・乳児期
- 重症の場合は生まれてすぐに「チアノーゼ」(唇や顔色が青紫色になる)が現れることが多い
- 呼吸が速い、苦しそう、ミルクの飲みが悪い、体重が増えない
- 手足が冷たい、ぐったりしている
- 不整脈が現れる場合も
□ 幼児期~学童期・思春期
- 軽症の場合は無症状のことも
- 息切れ、疲れやすさ、動悸
- 運動したときの呼吸困難
- 不整脈(動悸、失神、めまいなど)がきっかけで見つかることも
5. どうやって診断するの?
乳児健診や学校健診、風邪などでの病院受診時に「心雑音」(心臓の音の異常)をきっかけに疑われ、さらに詳しい検査が行われます。
主な検査
- 心臓超音波検査(心エコー)
三尖弁の位置・形、右心房・右心室の大きさ、弁の逆流、心房中隔欠損の有無や、心臓全体の血液の流れなどを詳しく調べる - 心電図
心臓のリズム異常、不整脈の有無、右心房・右心室への負担 - 胸部レントゲン
心臓や肺の大きさ、血流の状態を確認 - 心臓カテーテル検査、MRI、CT
詳しい心臓の構造、血流、圧力などを調べ、手術計画に役立てます
6. 治療の方針
エプスタイン病は、症状や重症度、心臓の構造・血流の異常の程度によって、治療の内容が大きく異なります。
□ 経過観察
- 症状が軽い場合は、定期的な心エコーや診察で経過観察のみで済むことも
- 体調や心臓の機能、逆流の程度、不整脈の有無を長期的にチェック
□ 薬物療法
- 心不全の症状や不整脈を抑えるための薬が使われることがあります
- 利尿薬、強心薬、不整脈の薬など
□ カテーテル治療
- 心房中隔欠損症の穴を広げたり、血流を調整したりする目的で行われることもあります
□ 外科手術
- 症状が重い場合、成長や発育への影響が大きい場合、不整脈がコントロールできない場合は手術が必要です
- 三尖弁の修復(弁形成術)、人工弁置換、右心房や右心室の大きさを整える手術など、病状に合わせて方法が選ばれます
- 合併症が複雑な場合、「フォンタン手術」など単心室症の手術が必要になることも
7. 手術後・長期的な経過
□ 手術の効果
- 手術により症状が改善し、多くの子どもが成長し、普通の生活や学校・運動に参加できるようになります
- ただし、三尖弁の逆流が再び現れたり、右心室の働きが弱くなる場合もあり、長期的な経過観察が必要です
□ 長期的な注意点
- 不整脈が起こりやすいため、定期的な心電図やホルター心電図(長時間心電図)でモニタリングが必要
- 心不全症状や運動時の息切れ、疲れやすさなどにも注意
- 心内膜炎(心臓内に細菌がつく感染症)のリスクがあるため、歯みがきや口腔ケア、歯科治療時の抗生剤使用が必要な場合も
8. 日常生活とケア
- 軽症例では、通常の学校や保育園、習い事や運動もほとんどの場合可能です(主治医と相談)
- 発熱、息切れ、動悸、失神、顔色の悪さなど体調の変化があればすぐに受診
- 予防接種や健診も主治医と相談しながら進めましょう
- 不整脈がある場合、スマートウォッチや家庭用心電計でのモニタリングも有用なことがあります
9. ご家族へのメッセージ
お子さんが「エプスタイン病」と診断されると、初めて耳にする病名や手術の話、将来の見通しに不安や戸惑いを感じるのは当然です。
ですが、現代の医療では多様な治療法があり、多くの子どもたちが元気に成長し、学校や社会で活躍できるようになっています。
ご家族がひとりで悩まず、医療スタッフとしっかり話し合い、分からないことや心配なことはどんな些細なことでも相談してください。お子さんの成長と笑顔のために、ご家族と医療チームが一丸となってサポートしていきます。