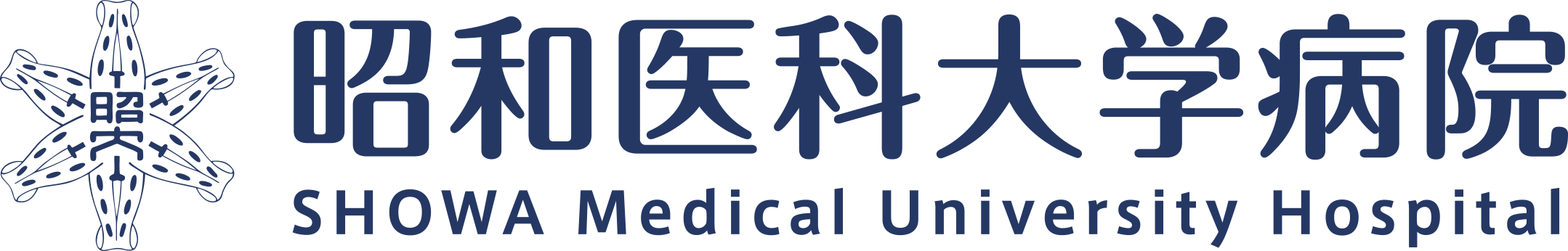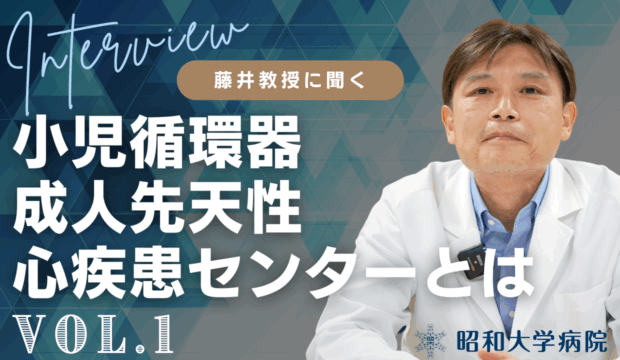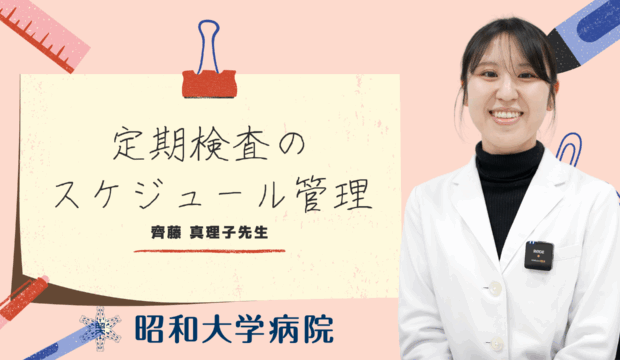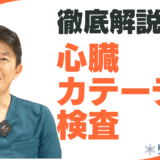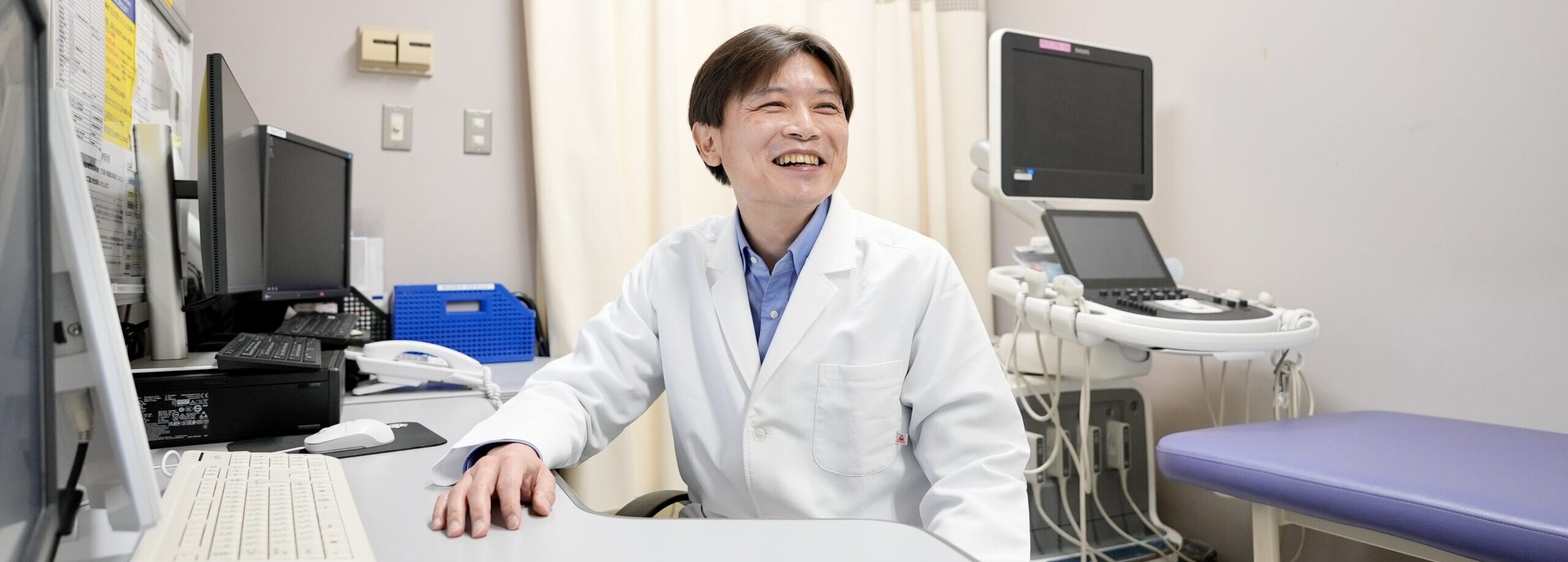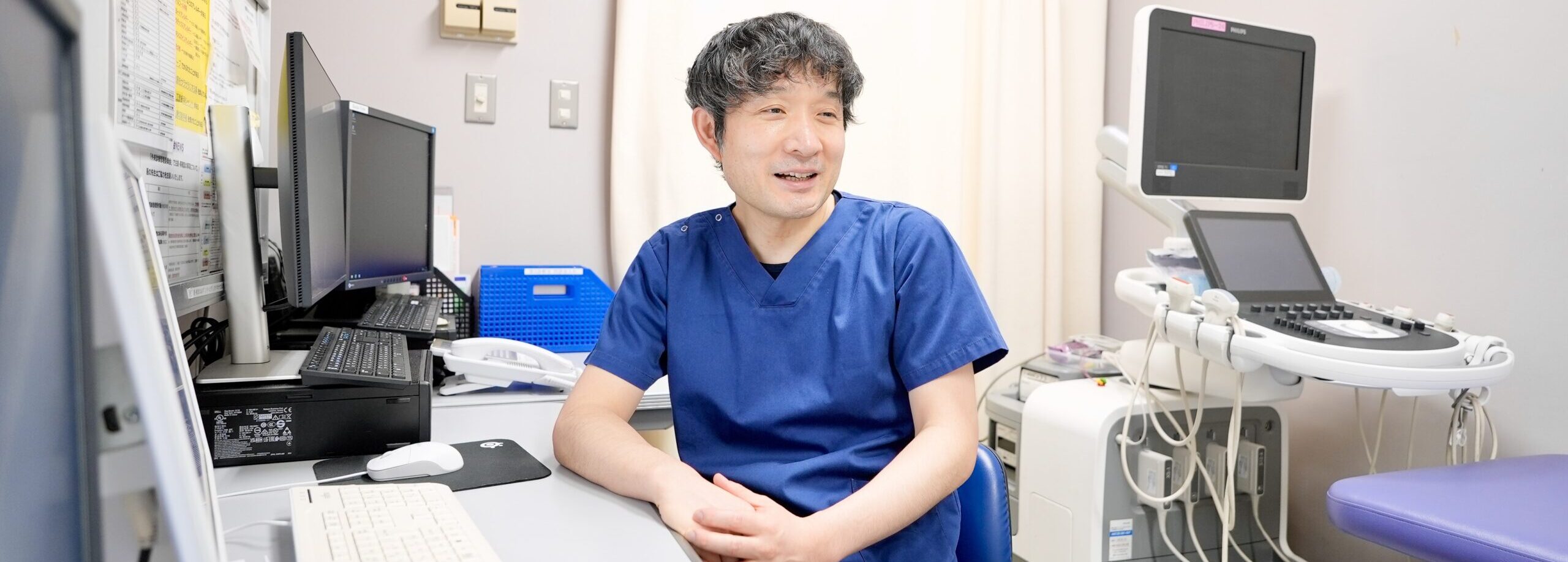こんにちは。昭和医科大学病院 小児循環器・成人先天性心疾患センターの喜瀬 広亮です。
本日は、小児の肺動脈弁狭窄についてご説明いたします。
小児の肺動脈弁狭窄とは──カテーテル治療で改善が期待できる心臓の病気
肺動脈弁狭窄とは?
肺動脈弁狭窄(はいどうみゃくべんきょうさく)は、心臓から肺に向かう血液の通り道である「肺動脈弁」が狭くなってしまう先天性心疾患の一つです。
この弁は、本来血液を一方向にだけ流す「逆流防止弁」のような役割を持っていますが、そこが狭くなると、血液が肺に送り出されにくくなります。その結果、心室(特に右心室)に大きな負担がかかってしまうのです。
どのくらいの頻度で見られる病気?
肺動脈弁狭窄は、先天性心疾患の中でも珍しい病気ではありません。発症頻度としては全体の5〜10%程度を占めており、比較的よく見られる心臓の病気のひとつです。
重症度によって異なる症状と治療方針
肺動脈弁狭窄には軽症から重症までさまざまな程度があり、症状や治療の必要性はその重症度によって異なります。
軽症の場合
-
自覚症状がほとんどなく、経過観察のみで治療の必要がないことも多くあります。
中等度の場合
-
疲れやすい
-
不整脈が出る
-
右心室のポンプ機能が落ちてくる
などの症状が現れることがあります。将来的な心機能の低下を防ぐためにも、適切なタイミングでの治療が検討されます。
重症の場合
-
新生児期からチアノーゼ(唇や指先が紫色になる)などの症状が出ることもあり、早期の治療が必要になります。
治療はカテーテルによるバルーン拡張術が主流
肺動脈弁狭窄の治療は、カテーテル治療が一般的です。具体的には、
-
足の付け根の血管から細い管(カテーテル)を挿入し、
-
狭くなった弁の部分にバルーン(風船)を通して膨らませることで、
-
狭窄した弁を押し広げ、血流を改善します。
この治療法は身体への負担も比較的少なく、手術に比べて回復も早いのが特徴です。重症度や心臓の構造によっては外科手術が必要となるケースもありますが、多くの患者さんがカテーテル治療で改善しています。
治療後の経過と注意点
治療によって肺動脈弁狭窄が改善された場合、多くの子どもたちは制限のない日常生活を送ることができます。
ただし、注意すべき点もあります:
-
一部の患者さんでは弁の再狭窄が起こることがあります。
-
カテーテル治療後に弁の逆流が見られるケースもあり、定期的な心エコーなどでの経過観察が重要です。
-
必要に応じて複数回の治療を行うこともあります。
最後に──安心して治療を受けるために
肺動脈弁狭窄は、比較的よくある先天性心疾患であり、治療法も確立されています。特にカテーテル治療は安全性が高く、多くの患者さんが回復して元気に日常生活を送っています。
「心臓の弁が狭い」と聞くとご家族は不安になるかもしれませんが、担当医とよく相談し、治療の方法や流れを理解することで、安心して治療に臨んでいただけるはずです。