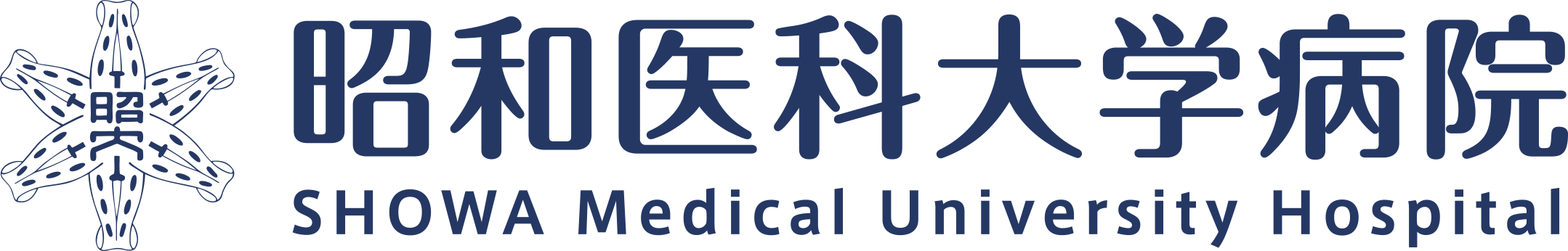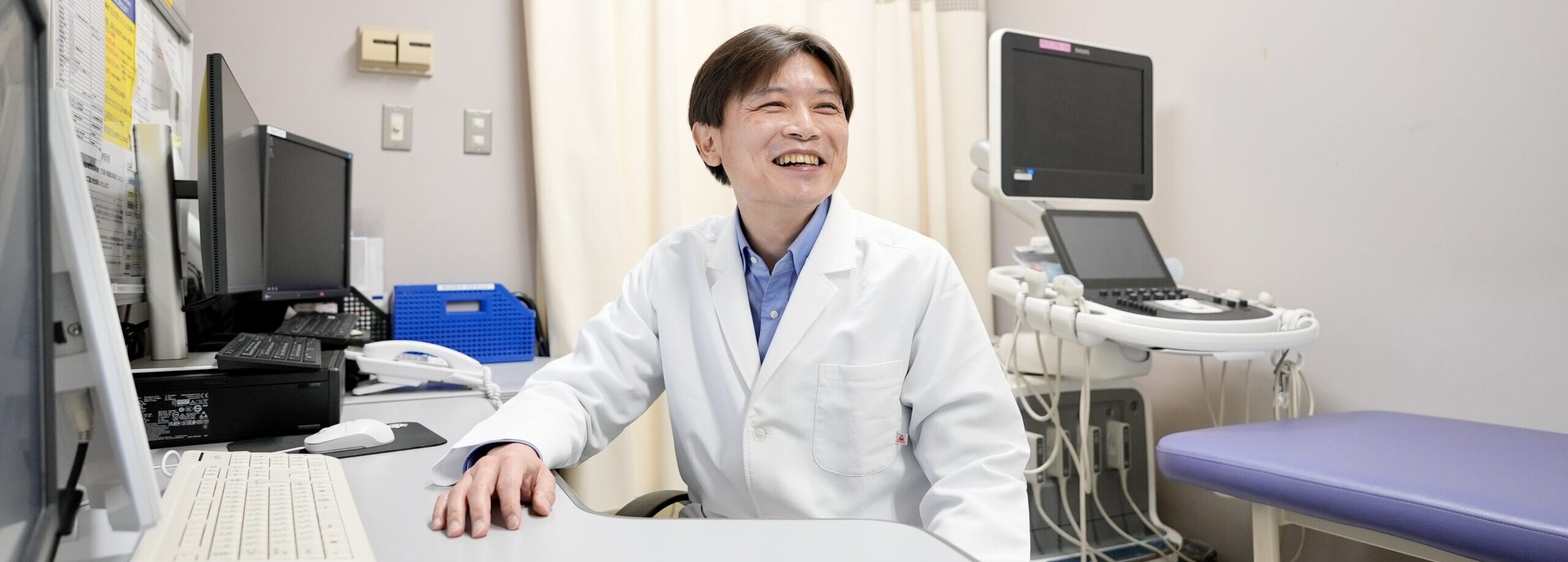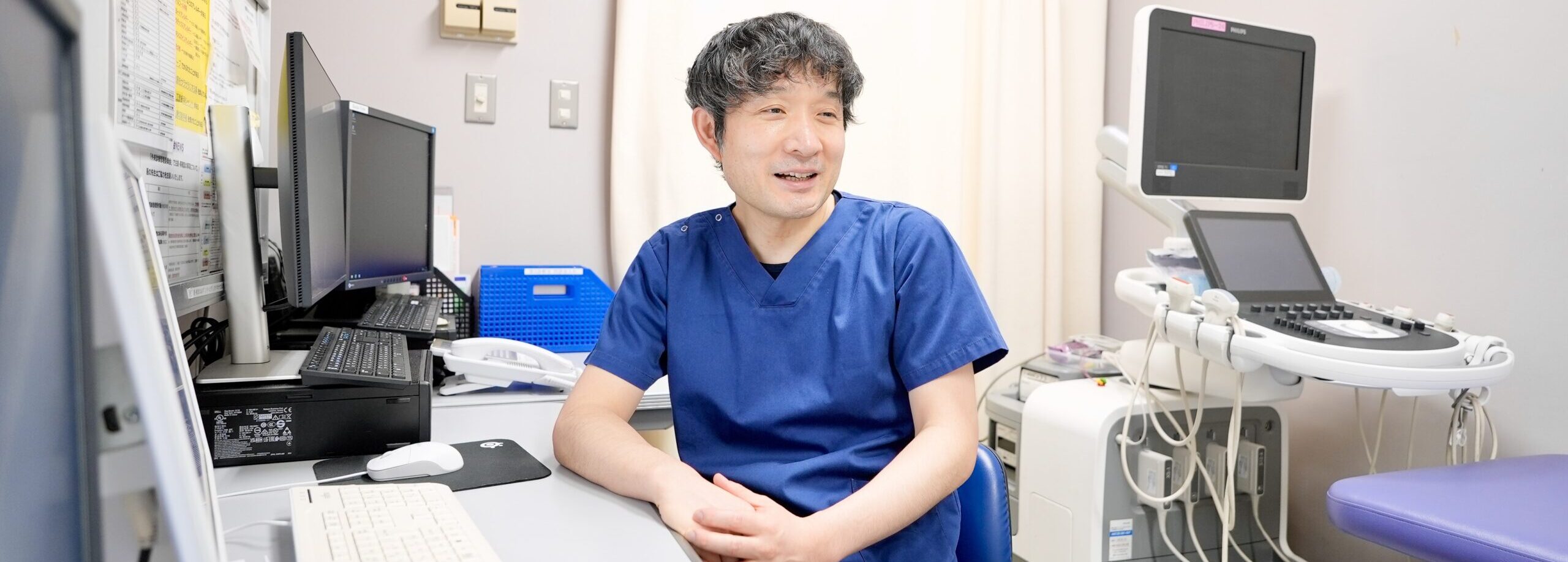小児の左心低形成症候群について
-お子さまの「左側の心臓が小さい病気」をやさしく解説します-
1. 左心低形成症候群とは
左心低形成症候群(さしんていけいせいしょうこうぐん、HLHS:Hypoplastic Left Heart Syndrome)は、赤ちゃんが生まれつき持っている心臓の病気のひとつで、非常にまれでかつ重症度の高い先天性心疾患です。
この病気では、心臓の「左側」が十分に発達しておらず、左心房、左心室、大動脈、僧帽弁、そして大動脈弁が極端に小さい、あるいはほとんど機能していない状態となります。
【正常な心臓のしくみ】
- 左心房と左心室がしっかり発達しており、肺で酸素を受け取った血液を全身に送り出す役割を果たす
- 大動脈は太く、全身へ効率よく血液を運ぶ
【左心低形成症候群の場合】
- 左心房や左心室がきわめて小さく、血液を送り出せない
- 大動脈も細くて全身へ血液が届きにくい
- そのため、生きていくためには右心室や特殊な血液の流れに頼るしかありません
2. なぜ起こるの?
左心低形成症候群は、お母さんのお腹の中で赤ちゃんが成長する過程で心臓の左側の構造が十分に発達しなかったことが原因で起こります。
原因は多くの場合不明で、ご両親のせいではありません。まれに遺伝や他の先天性異常をともなうこともありますが、ほとんどは偶然に起こるものです。
3. 左心低形成症候群があるとどうなるの?
この病気があると、赤ちゃんが生まれてすぐ、あるいは数日以内に深刻な症状が現れます。
□ チアノーゼ(皮膚や唇が青紫になる)
- 肺で酸素を受け取った血液が、全身に送られず、右心室から大動脈へ間接的に流れるしかありません
- 酸素が足りない血液が体に流れることで、皮膚や唇が青紫色になります
□ 呼吸が苦しそう
- 血液循環がうまくいかず、息が荒くなったり、呼吸が速くなったりします
□ ミルクの飲みが悪い、体重が増えない
- 酸素不足や心臓への負担のため、ミルクの飲みが悪く、体重が増えない、元気がないなどの症状が現れます
□ ショック状態
- 動脈管(出生直後は開いている血管)が自然に閉じてしまうと、全身への血液がほとんど送れなくなり、命にかかわる重いショック状態になります
4. どのように診断されるの?
多くの場合、生まれてすぐにチアノーゼや呼吸困難が現れるため、医師が診察やモニターなどで異常に気づきます。妊娠中の超音波(胎児エコー)検査で見つかることも増えています。
主な検査
- 心臓超音波検査(心エコー)
心臓の構造や血流の状態、左心房や左心室の発育度合い、大動脈や弁の状態などを詳しく調べます。 - 胸部レントゲン
- 心電図
- 血液検査(酸素飽和度など)
- 心臓カテーテル検査やCT/MRI 手術前の詳細な評価や治療計画に使われます。
5. 緊急の対応と治療方針
□ 出生直後の対応
- 赤ちゃんが生まれるとき、「動脈管(どうみゃくかん)」という特別な血管が開いている間は、右心室から全身へ血液を送ることができます。
- この動脈管を「プロスタグランジンE1」という薬で開いたままにし、救命につなげます。
- 酸素投与や点滴、呼吸管理など、NICU(新生児集中治療室)で厳重な管理が必要です。
□ 根治的治療(段階的手術)
左心低形成症候群は、自然には治らない病気です。
救命と将来の生活のために、**3段階の手術(Norwood手術→Glenn手術→Fontan手術)**が必要となります。
6. 段階的な手術(3ステップ)
- Norwood(ノーウッド)手術 【生後数日~2週間以内】
- 小さい大動脈を大きく作り直し、右心室から全身へ血液を送る新しい道を作ります
- 肺への血液もバランスよく流れるよう「シャント」という人工血管を使います
- Glenn(グレン)手術 【生後4~6か月ごろ】
- 上半身から心臓に戻る静脈の血液を、直接肺へ流すバイパスを作ります
- 心臓の負担をさらに減らし、酸素の多い血液を体に送りやすくします
- Fontan(フォンタン)手術 【2~4歳ごろ】
- 下半身から戻る静脈の血液も肺へ直接流す道を作り、右心室の負担を最小限にします
- この段階で、「1つの心室で全身と肺の血流をコントロール」できるようになります
7. 術後・長期的な経過と注意点
これらの手術を乗り越えることで、多くのお子さんが成長し、日常生活や学校生活に復帰することが可能になります。ただし、普通の心臓の働きとは異なるため、一生にわたる注意とケアが必要です。
□ 術後の合併症
- 心不全(心臓のポンプ機能が低下する)
- 不整脈(心臓のリズムの異常)
- 肝臓や腎臓など他の臓器の負担
- 血栓(血管に血のかたまりができやすくなる)
- たんぱく漏出性胃腸症などの特殊な合併症
□ 日常生活
- 食事や運動、学校生活は主治医と相談しながら行います
- 体調の変化(息切れ・むくみ・顔色の変化・発熱など)に気を配り、早めに受診を
- 感染症予防(手洗い・うがい・歯みがき・予防接種など)がとても大切
□ 定期的なフォローアップ
- 退院後も、定期的に心臓超音波検査・心電図・血液検査などを受け続けます
- 小児循環器専門医による長期的なサポートが欠かせません
8. 左心低形成症候群と向き合うご家族へ
この病気と診断されると、初めて聞く病名や難しい手術の話、将来の見通しについて、とても大きな不安や悲しみ、迷いを感じることはごく自然なことです。ですが、今の医療では多くの子どもたちが段階的な治療を受けて、元気に成長し、学校や社会生活にも復帰しています。
大切なのは、ひとりで抱え込まず、信頼できる医療スタッフと一緒に治療やケアを進めることです。
どんな疑問や心配も、遠慮せずに相談してください。ご家族の前向きな気持ちや愛情が、お子さんにとって最大の支えになります。
9. まとめ
- 左心低形成症候群は、心臓の左側が発達せず、右心室に頼って全身の血液循環を行う難しい病気です
- 生まれてすぐに症状が出て、緊急の治療と段階的な手術が必要です
- Norwood手術、Glenn手術、Fontan手術という3段階の手術を経て、多くの子どもが成長できる時代になっています
- 一生にわたり専門医のフォローと体調管理が大切です
- ご家族と医療チームが力を合わせて、お子さんの未来を守っていきましょう